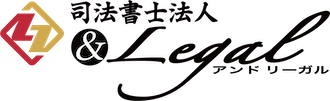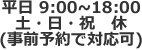家族信託について ~その6~(アパートオーナーの資産管理)
2022.04.08 Fri
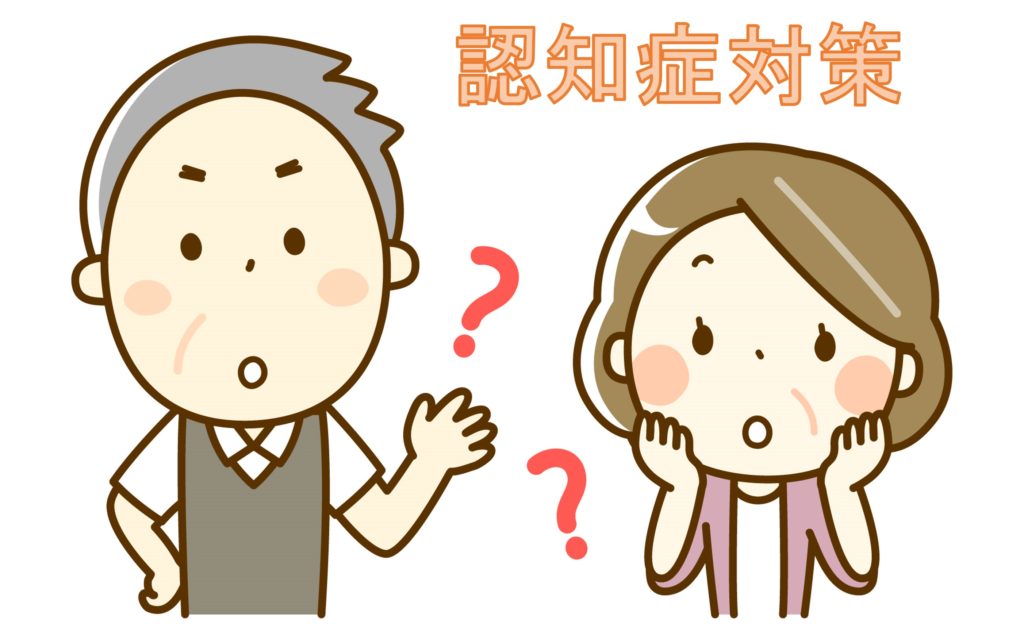
今回は、認知症対策として利用する家族信託の事例として、アパートを所有している高齢のお父さんを想定してみます。

事例
自宅とアパートを複数所有している父がいます。
妻は既に他界しており、子供は長男の長女の2名です。
現在、父は自分でアパートの管理をしていますが、高齢のためか最近物忘れが増えてきました。また、父は持病をもっており、入退院を繰り返しています。今後、物忘れが酷くなり認知症発症の心配や持病の悪化などが心配されます。そうすると、アパートの入居希望者や退去者が出た場合の契約手続きなどの賃貸管理、アパートの外壁や屋根の塗装、リフォームなどの修繕などが出来なくなってしまう心配があります。
父は、自宅とアパート2棟を所有しています。父の希望は、自宅は同居してくれている長女に自分が亡くなったら相続させたい。アパート2棟は長男、長女にそれぞれ相続させたいと考えています。
◆例えばこの事例で何もしなかった場合
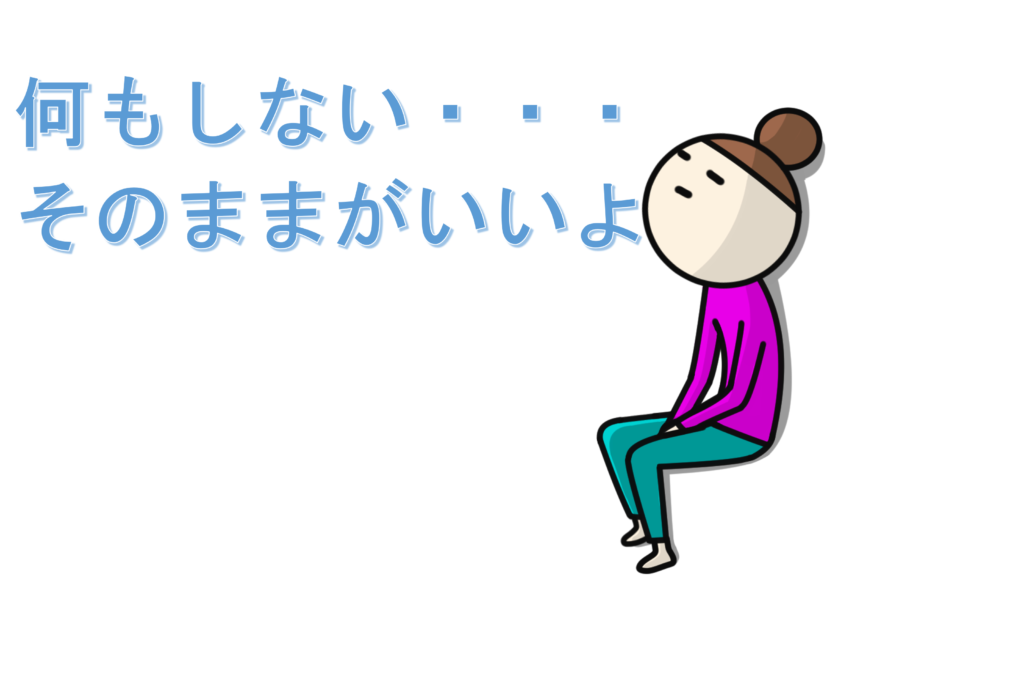
認知症などで父の判断能力が喪失した場合には、アパートの賃貸管理や売却、大規模修繕、建て替えなどの対策が出来なくなってしまいます。また、父が他界し相続が開始した場合、遺言を作成していないと相続人間で遺産をどのようにわけるか協議が必要となってしまいます。
◆成年後見制度を利用した場合

父は資産が多数あるので、親族が後見人にはなれず、司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人に選任される可能性が高いです。そうすると基本的に父のための支出しか認められません。アパートの大規模修繕や建て替え、売却などの効率的な財産管理が出来なくなってしまいます。おそらく成年後見人と裁判所の監督下では、大規模修繕ではなく売却処分になり、家族の考えとは違う処分がなされる可能性が高いです。成年後見制度の下では、建て替えはほぼ不可能です。
◆家族信託を利用した場合
-1024x832.jpg)
長男が相続する予定のアパートについては、長男を受託者、長女が相続する予定の自宅とアパートについては長女が受託者として、利益(家賃)を受ける受益者は父とする信託契約を2契約締結します。(アパートを信託契約2契約とすると損益通算が出来なくなります。詳しくは信託契約を締結する際に専門家にご相談ください)

信託契約(長男)
委託者 父
受託者 長男
受益者 父
信託財産 アパート①
信託の終了 父の死亡
信託終了後の財産 長男に帰属させる

信託契約(長女)
委託者 父
受託者 長女
受益者 父
信託財産 自宅、アパート②
信託の終了 父の死亡
信託終了後の財産 長女に帰属させる
この様な信託契約を締結すると、委託者と受益者は父で、名義だけを受託者である長男と長女にしています。そのため、不動産取得税や贈与税、譲渡所得税は発生しません。また、父が元気なうちは、父、長男、長女が共同でアパートを管理する事が出来ます。父の判断能力が低下し管理が難しくなった場合は、受託者である長男、長女がそれぞれの信託財産として管理しているアパートを管理していく事になります。財産の処分権限は、長男、長女それぞれが持っていますので、各々が入退去時の契約から大規模修繕、売却などの処分をする事が出来ます。
将来相続が開始したときも、どの財産を誰が相続するのかを予め決めているので、相続でもめる事はありません。
このように家族信託は、財産管理のみならず生前に財産の帰属先を決めることが出来ます。相続開始後の相続人間で話し合って決めなければならない遺産分割は、もめる原因の一つですが、家族信託では、生前に父を交えて話合い財産の帰属先を決める事が出来るので、円満な相続対策が出来ます。